2007年10月30日
ヨーウィー
ヨーウィーとは、オーストラリアの先住民アボリジニーの間で古くから伝わる獣人の事です。
この生物の目撃例は実に3000件を超えており、身長1.8~3m程で、全身が毛むくじゃらで、首が殆ど無く、腕が長くて筋肉質で、直立二足歩行するそうです。
ヨーウィーという呼称が使われる様になったのは、比較的最近の1970年代に入ってからだそうで、そもそもオーストラリアには、先住民であるアボリジニーが「ガバ」と呼んで恐れる怪物がいたそうです。
ガバは「悪魔の穴」と呼ばれる洞窟に住んでいるとされていたそうで、19世紀に移住してきた西洋人達は、全身に毛の生えた怪物がニューサウスウェールズ地方に出ると噂し、まんま「Hairy man」等と呼んでいたそうですが、いつしか「Yahoo」と呼ぶ様になったそうです。
これは、アボリジニーの言葉での「邪悪な霊」、「悪魔」等を示す言葉に由来したという説もありますが、実際には、1726年に作家のジョナサン・スウィフトが書いた『ガリバー旅行記』に登場する野蛮な亜人、「Yahoos」からとられたのではないかとも言われています。
そして、「Yahoo」から「Yowie」にとって変わったそうです。
ヨーウィーの最も有名な目撃例は、チャールズ・パーカーという人物によるものでしょう。
1912年11月10日、パーカーは、シドニーから測量の為に、ニューサウスウェールズ州南部のクーナバラブランにある山脈沿いの密林でキャンプをしていたそうです。
既にこの頃、巷では毛むくじゃらの怪物の噂が流れており、彼もそれを耳にしていたそうですが、信じていなかったそうです。
ところが、キャンプ2日目の夜、パーカーは奇妙な獣の鳴き声を聞き、周囲の様子を伺っていると、焚き火から20m弱の場所に、巨大な人の様な生物を発見したそうです。
その生物は、頭がやけに小さく、大きな目が窪んでおり、2本の牙が生えていたそうですが、顔は人間的に見えたそうです。
また、全身が褐色の毛で覆われ、背中と肩の毛が特に長く、脛が異様に短い割には、腕が異様に長く、手足が大きかったそうです。
その生物は、その場にしばらく唸りながら直立し、体を震わす度に毛が揺れ、やがて胸を叩くと、闇の中に走り去っていったそうで、画像は、後にパーカーが記憶をもとに描いた生物のスケッチです。
また、1980年4月には、ネットロス・フィールズという町に住むレオ・ジョージという人物が、自宅近くで林の中へ去る身長2m程の毛むくじゃらの生物を目撃し、同時に30cm程の足跡が残っている事に気づき、近くにはその生物が捕食したと思わしき、ズタズタに引き裂かれたカンガルーの死骸が転がっていたそうです
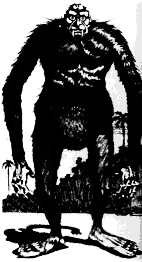
この生物の目撃例は実に3000件を超えており、身長1.8~3m程で、全身が毛むくじゃらで、首が殆ど無く、腕が長くて筋肉質で、直立二足歩行するそうです。
ヨーウィーという呼称が使われる様になったのは、比較的最近の1970年代に入ってからだそうで、そもそもオーストラリアには、先住民であるアボリジニーが「ガバ」と呼んで恐れる怪物がいたそうです。
ガバは「悪魔の穴」と呼ばれる洞窟に住んでいるとされていたそうで、19世紀に移住してきた西洋人達は、全身に毛の生えた怪物がニューサウスウェールズ地方に出ると噂し、まんま「Hairy man」等と呼んでいたそうですが、いつしか「Yahoo」と呼ぶ様になったそうです。
これは、アボリジニーの言葉での「邪悪な霊」、「悪魔」等を示す言葉に由来したという説もありますが、実際には、1726年に作家のジョナサン・スウィフトが書いた『ガリバー旅行記』に登場する野蛮な亜人、「Yahoos」からとられたのではないかとも言われています。
そして、「Yahoo」から「Yowie」にとって変わったそうです。
ヨーウィーの最も有名な目撃例は、チャールズ・パーカーという人物によるものでしょう。
1912年11月10日、パーカーは、シドニーから測量の為に、ニューサウスウェールズ州南部のクーナバラブランにある山脈沿いの密林でキャンプをしていたそうです。
既にこの頃、巷では毛むくじゃらの怪物の噂が流れており、彼もそれを耳にしていたそうですが、信じていなかったそうです。
ところが、キャンプ2日目の夜、パーカーは奇妙な獣の鳴き声を聞き、周囲の様子を伺っていると、焚き火から20m弱の場所に、巨大な人の様な生物を発見したそうです。
その生物は、頭がやけに小さく、大きな目が窪んでおり、2本の牙が生えていたそうですが、顔は人間的に見えたそうです。
また、全身が褐色の毛で覆われ、背中と肩の毛が特に長く、脛が異様に短い割には、腕が異様に長く、手足が大きかったそうです。
その生物は、その場にしばらく唸りながら直立し、体を震わす度に毛が揺れ、やがて胸を叩くと、闇の中に走り去っていったそうで、画像は、後にパーカーが記憶をもとに描いた生物のスケッチです。
また、1980年4月には、ネットロス・フィールズという町に住むレオ・ジョージという人物が、自宅近くで林の中へ去る身長2m程の毛むくじゃらの生物を目撃し、同時に30cm程の足跡が残っている事に気づき、近くにはその生物が捕食したと思わしき、ズタズタに引き裂かれたカンガルーの死骸が転がっていたそうです
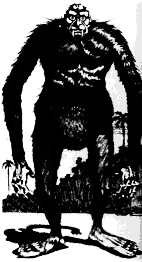
2007年09月13日
ツチノコ

ツチノコとは、1970年代以降、日本全国で次々目撃報告が寄せられ、一大ブームを巻き起こした未確認生物です。
古くは江戸時代に書かれた書物の『古事記』や、百科事典『和漢三才図会』に、深山に棲む「野槌(ノヅチ)」として紹介されています。
ツチノコという名は、その形状が槌に似ている事からきており、先のブームで広く定着しましたが、もともとは京都市北部と鈴鹿山脈、吉野熊野一帯、四国北部等で使われていた一地方の一方言に過ぎず、地域により呼び方は様々あり、「タワラヘビ」「バチヘビ」等とも呼ばれています。
目撃証言によれば、体長30cm~85cmで、皮膚の色は黒または茶褐色、体のわりに大きな頭とビール瓶の様な太い胴をしていますが、尻尾はネズミの様に細く、尺取虫の様に体を上下にくねらせて移動し、時には数mも高く跳ねる事もあるそうです。
また、噂としては、ツチノコは春から秋に出現し、主に昼間に単独で行動し、胴を張って尾部で垂直に立つ事も出来、鳴いたり、瞬きしたり、生意気にもいびきをかいて寝るそうです。
2000年5月21日の朝8時頃、岡山県吉井町の中島正夫氏が田んぼで草刈り作業中、ツチノコと思われる生物が草刈り機で傷つき、田んぼ脇の水路へ逃げていったそうです。
そしてその3日後、そこから200m程離れた水路で、同一生物と思われる死骸が発見されたのです。
死骸には15cm程の傷があり、可哀想に思った発見者の青山文子氏が死骸を土に埋めてやったそうです。
中島・青山両氏の証言によれば、この生物は体長70~80cmで、頭は大きく丸く、胴の太さはビール瓶程で、全体は灰色に近い黒色ですが、腹部は紫がかった白色だったそうです。
また、尺取虫の様に身をくねらせていたそうです。
このツチノコらしき生物が現れたという話は広まり、町役場が「つちのこだより」なる緊急号外を出す等、大騒ぎになりました。
そして6月5日に、この生物の死骸が掘り出されたそうなんですが、かなり傷んでいて正体が分からなかった為、町役場は、倉敷市の川崎医療福祉大学に分析を依頼しました。
すると6月28日に、分析に当った生物爬虫類学教授の佐藤國康氏が、ウロコの様子や後牙を持つ事などから、この死骸の正体は日本全国に生息する蛇、ヤマカガシであると発表したのです。
しかし、目撃証言の中には通常のヤマカガシと一致しない特徴も見られる為、目撃された生物とこの死骸とが同一ではない可能性もあります。
吉井町では以前からツチノコらしき生物の目撃があったとの話もあり、ツチノコ生存の可能性が否定された訳ではないと思います。
2007年09月08日
メガラニア

1975年、オーストラリアはニューサウスウェールズ州セスノックの農民が、納屋のそばに現れた巨大なトカゲを目撃した。そのトカゲは体長が9メートルを優に超え、体重は900キロ以上ありそうに見えたという。体は灰色でぶちがあり、背中や尾には黒い縞模様があったという。
また同年の同地方で、マイク・ブレイクによっても巨大トカゲが目撃されている。ベランダでのんびりくつろいでいた所、体長7メートルほどのトカゲが現れ、辺りをうろついた後、畑のなかに去っていったという。
さらに同年、ワタガンズ地方では二人の農夫が巨大トカゲに遭遇した。森を通り抜けようと車を走らせていると、丸太のようなものに道をふさがれたという。二人が車から降りてそれをどかそうとすると、それは動き出し、森の中に消えていったという。木だと思ったそれは一匹のトカゲだったというのである。道幅は7メートルほどだったが、頭と尾は道からはみ出し、見えなかったという。
その他1979年には、同様のトカゲのものと思われる大きな足跡が発見されている。
現在のオーストラリアに生息するトカゲは体長2.4メートルほどのものが最大とされ、これほど大きなものは知られていない。
だが過去のオーストラリアには、この証言に合致する生物が実際に生息していた。体長が9メートル以上にもなる巨大トカゲ「メガラニア」である。
現在では絶滅したとされているが、これまでに見つかった化石から、少なくとも完新世初頭(約1万年前)まで生きていたことが分かっている。
巨大トカゲの目撃報告は現在も後を絶たず、実は密かに生き延びているのではないか、と考える研究者も少なくない。
メガラニアが生き残っているという確たる証拠は無いが、逆に、完全に死に絶えたと言い切るほどの根拠も無いのである。
特徴
体長9メートル以上のオオトカゲ
体重は900キロ程度か
体色は灰色で、ぶちがあり、背中から尾にかけて黒っぽい縞模様があったとの証言も
2007年09月05日
ジェヴォーダンの獣


1764年から1767年までの間、フランス中南部にあるジェヴォーダン地方にて、雌牛サイズの狼の様な獣の怪物が現れたと言われています。
その怪物は「ベート」と呼ばれ、歩いている時は鈍重そうですが、走り出すとかなり速いらしく、120人以上の村人を食い殺し、近隣の人々を恐怖に陥れたそうです。
初めてベートがジェヴォーダンに姿を現したのは、1764年7月の初め頃。
ランゴーニュで若い女性が突然現れたその怪物に襲われ、彼女の牡牛達が追い払ったという事件を皮切りに、続いてヴィヴァレー地方のサン・テチエンヌ・ド・リュグダレス村の、ジャンヌ・ブーレという14歳の少女がいなくなり、翌日、村人によってその少女の食い殺された死体が発見されたそうです。
村にベートの噂が流れ始めた8月には、ピュイ・ローランの近くで、15歳の少年と少女が食い殺されたそうです。
やがて、ベートは新聞に取り上げられ、事態を知ったルイ15世は、ベートを退治すべく、狩猟隊の竜騎士達を派遣しました。
しかし、ただでさえ貧困生活なのに、村人達は畑仕事から招集され、ベート狩りに強制的に参加させられたそうです。
しかも、肝心の竜騎士達は贅沢に飲み食いした挙げ句、何の成果も上げず、とっととベルサイユへ帰還してしまったそうです。
その後続として王宮付属の狩猟隊デンヌヴァル父子が派遣されるも、これまた成果を上げられず帰還。
そして、3度目の正直とばかりに期待され、狩猟隊ボーテルヌ父子が派遣されたそうなんですが、なんと彼らは、偽者を使ってベートを退治したと宣言し、しかも王宮の掲示した懸賞金まで手に入れるという、詐欺を行ったそうなんですよ。
そんなこんなで、ベートは退治された事になり、事件は解決したと当時の新聞までも書きたてました。
しかし、12月2日、ムーシェ山の南東の斜面にあるオンテス・オーの部落で、7歳の少年がベートに食い殺されたそうなんですよ。
この時、事件を目撃した14歳のジャック・ドゥニ少年によれば、ベートは背中に1本の縞が走り、脇腹には黒と焦げ茶の斑点があって、狼では無いと強く主張していたそうです。
その後もベートは多くの人々、特に女・子供を食い殺しました。
これ以上犠牲者を出さない為に、ベートを殺すしか無いと、村人達は結束し、1767年6月19日の狩り出しには、漁師と勢子300人が参加したと言われています。
その日、地元の領民ジャン・シャステルは、オーヴェールのソーニュに位置を構え、彼が聖マリアの連祷を読んでいると、ベートが彼の前に不意に姿を現したそうです。
彼は冷静に、本をたたみ、眼鏡をはずしてポケットにいれると、銃を肩にあて発砲しました。
すると、鉛のマリア像から作った弾丸がベートに当たり、ついに人々を苦しめ続けた人食い獣を殺したのです。しかし結局、ベートの正体が何であったのかは不明です。
単にデカくて凶暴な狼やハイエナだという説から、狼の毛皮を被って、農家からお金を盗ろうとした者もいる事から、ベートは実は人間だったのではという説や、熊説、狼男説、宇宙人説までありますが、事件背景が入り組んでおり、当時の記録も少ない事から、どうにも確信は得られません。
2007年09月02日
オウルマン

オウルマンとは、イギリス南西部に現れた、まるで人間とフクロウ(オウル)が合体した様な姿のUMAです。バードマンとも呼ばれています。
体長は1.5m程で、全身が灰色の羽毛で覆われ、大きな翼があり、その翼の先に指があるそうです。
そして赤く鋭い目に、尖った耳を持ち、足には鉤爪があるそうです。
1976年4月17日、イギリスのコーンウォール州モウマン村の教会の森で、当時12歳のジューン・メリンダと9歳の妹ビッキーが、教会の塔の上を翼をばたつかせて飛んでいるオウルマンを目撃し、スケッチにその姿が残されています。
また、同年7月4日には、当時14歳のサリー・チャップマンが、友人のバーバラ・ペリーと森でキャンプをしている時、「ヒューッ」という音を耳にし、その方を見ると、松の木の中央に翼の生えた灰色の怪人が立っていたそうです。
最初はハンググライダーをやってる人か何かと思ったそうですが、そいつは突然空高く舞い上り、何処かへ消えていったそうなのです。
その後もオウルマンは1978年6月に目撃されましたが、8月2日のフランス人観光客による目撃を最後に、ぱったりと姿を見せなくなったそうです。

オウルマンの正体としては、コウモリや鳥といった動物の誤認や人為的な悪戯だとは考え難く、宇宙生物説、何者かによって極秘に産み出されたキメラ生物説位しか考えられません。
また、1966年にアメリカのウエストバージニア州で目撃されたモスマンとの類似が指摘されていますが、真相は不明です。
2007年07月24日
リーン・モンスター

この怪物はアイルランド南西部コーク州のリーン湖で目撃されるUMAで
通称、リーン・モンスターと呼ばれている。
写真は1981年8月、プロカメラマンのパット・ケリーが撮ったもので
これがリーン・モンスターを捉えた唯一の写真とされている。
この怪物はネッシーによく似たタイプで
その体長も6~10mと大きい事から注目を集めている。
結構有名らしいロイ・マッカル博士という人も
この湖を2度も訪れ、現地調査を行っているそうです。
また、このリーン湖周辺の湖でも蛇のような怪物や、
ゾウとアザラシを合わせたような怪物が目撃されており
中々興味深い地域である。
だが、この辺りは人口も少なく、ほとんど湖の調査がされていないので
いまだに情報が乏しい。
生息地 アイルランド南西部
コーク州、リーン湖
体長 6m~10m
特徴 ネッシーとよく似ており
長い首と背中に2つのコブがある。
正体 プレシオサウルスの生き残り説
未知の哺乳類説など
2007年07月15日
ニュー・ネッシー

1977年4月25日、ニュージーランド沖で操業中の日本のトロール船 瑞洋丸(2,455t)が正体不明の死骸を引き上げた。
この死骸は大きさが10メートルほどもあり、大きなヒレ状の部分や長い首のような部分が見うけられた。
引き上げられた時点で既にかなり腐敗していて悪臭もひどく、衛生上の問題などからまもなく海中に投棄されたという。
これらの事実が写真付きで報道されると、未知の巨大生物、あるいは絶滅したはずの首長竜の死骸ではないかとの説が唱えられ、日本中が大変な騒ぎとなった。
この死骸は、報道されるうちに「ニュー・ネッシー」と呼ばれるようになった。(おそらく”ニュージーランド版ネッシー”と”新たなネッシー”を掛けたものであろう)
瑞洋丸に乗船していた矢野道彦氏が、死骸の体組織の一部や写真など数点の資料を保存していたため、帰国後それら資料の分析が複数の機関で行われた。
その結果を総合的に判断すると、正体はウバザメかその近縁種と考えるのが妥当であろうとされ、一応の決着をみた。
しかし直接の目撃者である田中船長ら瑞洋丸船員は、
腐敗臭が魚のそれとは違っていた
サメ類と違い、後ろにも一対のヒレがあった
サメと違い、首や尾の骨が正方形の硬いブロック状だった
などの特徴を挙げていたという。
現在でも、ときどき珍しい生物(深海魚など)が捕獲されたというニュースはあるが、「ニュー・ネッシー」ほどの大きな話題になったものもないだろう。



